- ホーム
- ほしのさとの想い
ほしのさとの想い
Our hope


人はみんな星のように、その人らしく光っています。
どの星も大きさや明るさは違えど、それぞれに輝いているように、誰しもかけがえのない存在です。
子どもたちが、人や自然と調和して育っていくまちの様子を「ほしのさと」と表現しました。
六瀬ほしのさと小学校は、まちの学校として地域や人を大切にします。
対話し、ともに何かをつくっていく本物の体験の中で、子どもたちは「自分らしさ」と出会っていきます。

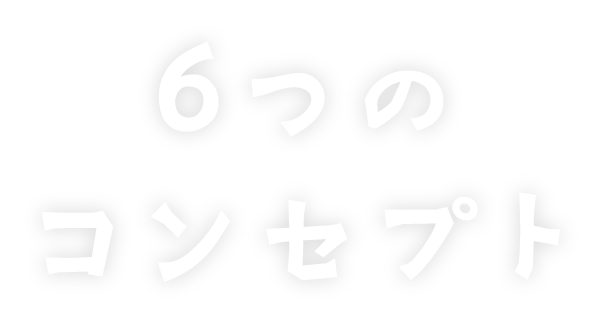


自己決定を尊重する
この学校ではだれも【えらぶ】を肩代わりしてくれない。やるのかやらないのか。どう学ぶのか。何に力を注ぐのか。全部自分で【えらぶ】。そうすると、自分は何が好きで、何が得意で、何が苦手なのかがわかってくる。それを積み重ねると、自分がどんな風に生きたいかが少しずつ見えてくる。そうするとそれが本当の意味で自分らしく生きることだとわかる。 自分で【えらぶ】ことが難しいこともある。そんな時は信頼できる大人や仲間の力を借りて自分で【えらぶ】を繰り返す。でもそれは【えらんでもらう】とは少し違うことも知ることが大切。時に自分らしく生きる道の途中で失敗することもある。だけど、その失敗は妙に納得感がある。納得感のある失敗は自分らしく生きる為の大きなヒントになり、幸せに生きる為の本物の授業でもある。 そんなことで、この学校は【えらぶ】をまんなかにおいた学校。

本物の体験を重視する
なんでもまず【やってみる】ことが全てのスタート。やってみて、やってみて、何度でも【やってみる】と、物の仕組みや理がなんだか妙にわかってくる。わかってくるとその先がどんどん知りたくなる。知りたくなったら、その先を探く深く突き詰める。それが探求するということ。探求していくと、どんなものごとでも国語や算数、社会、理科、道徳やそれ以外の沢山の学びが絡まっていることに気付く。とっても不思議だけど【やってみる】先で出会う学びはなんだかやる気がわく。やる気は集中力や根気といった仲間を連れてきてくれる素敵な存在。【やってみる】を通して自分らしく生きる為に本当に大切な力を身に付ける。 この学校の学びの出発点は本物を【やってみる】こと。そして最後までとことん【やってみる】こと。

対話を大切にする
わくわくする時。わからない時。たいへんな時。なやましい時。問題がおきた時。学校のルールを決める時。どんな時でも【はなす】ことがこの学校のルール。広い世界の中ではいつでも正解があるわけじゃない。大人が正解を持っているわけでもない。だから、子どもだって大人だっていつだって対等に【はなす】を大切にする。【はなす】を通して自分が生きる世界は自分の力でよりよく変えられることを知る。自分が人生の主人公だと知る。そんな学びがよりよい世界をつくる人をつくる。よりよい世界を生きるということは幸せな人生を生きるということ。
だから、この学校はどんな時でも【はなす】学校。

人・地域と共に学ぶ
学びの場は学校だけじゃない。どこだって誰だって何か素敵なことを教えてくれる存在。だからこの学校ではもっと外に目を向けて【つながる】。まずは地域と【つながる】。【つながる】となんだか地域のことがよく見える。困っている人。すごいことができる人。お話が好きな人。おもしろい人。優しい人。そんな人と【つながる】ことから学ぶ。困っている人を助けること。優しい人の優しさに触れること。すごいことを教えてもらうこと。【つながる】とみんなに支えられていることに気付く。そうするといろいろなことが自分ごとになってくる。【つながる】を通して地域を好きになって感謝する。この学校は感謝の気持ちを忘れず【つながる】学校。
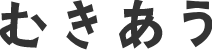
自分を見つめる
ここは自分の気持ち・考え方・行動・言動にしっかり【むきあう】を大切にする学校。人生生きていればうまくいくこと、いかないこといろいろなことが起こる。どんなことでもやりっぱなしはよくない。どんなことでも振り返りながら【むきあう】。なぜならそこに次へのヒントが隠れているから。はじめは信頼できる大人と一緒に【むきあう】。そして、少しずつ自分で自分と【むきあう】。自分と【むきあう】と自分を理解できる。そうすると、そんな自分が好きになる。自分を好きになれる人は自分を信じられる人。 ここは【むきあう】ことを通して自分も人も大切にする心を育む学校。

自分も人も大切にする
違いを認める
“人間はみんな違っている”そんな当たり前のことを認めあう学校。まずは自分を【みとめる】。自分は何が好きか、何が苦手かいろいろな自分を【みとめる】。それができる人はきっと自分と違う人を【みとめる】ことができる人になるから。その為にはいろいろな違いを経験することが大切。年齢や発達、しょうがいの有無など、学校で出会えるありとあらゆる違いを大切にする。そうすると、違うことが当たり前という気持ちが湧いてくる。それが本当の意味で違いを【みとめる】ということ。世界に目を向けるともっと多くの違いが存在する。そこに出会う前に、まずは自分の身の回りの違いを【みとめる】。それができる人は平和な世界をつくれる人。 だから、ここは自分も人も大切にして違いを【みとめる】学校。
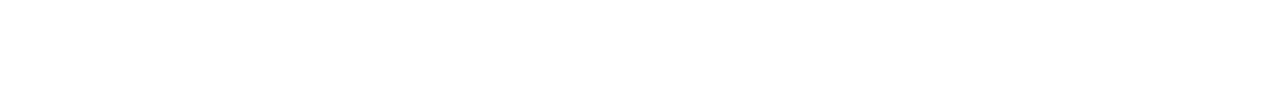
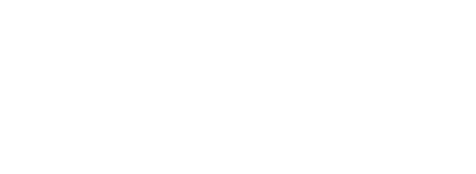
「6つのコンセプト」に象徴されるほしのさとでの学びの先に、
人生の軸となる「自分を信じる力」「当事者意識」「多様性の理解」という
3つの土台が育まれることを目指します。
その土台を礎に、「自分らしく幸せに生きる」「自分らしく社会に貢献する」
「違いを認め多様な人と共生する」という3つの視点を、
幸せな人生を生きる為の重要な要素と捉えます。
我々の思い描く未来は、学力や学歴という視点で人を測る世界ではなく、
本当の意味で一人ひとりの人間が幸せに生きる世界を創ることです。
そしてそれは、21世紀における教育の最大の役割であるとも考えています。


「育児」から「育自」へ
子育てをする親であれば、子どもの最善の育ちを願い、一生懸命子どもを育てようとします。
まさにそれが【育児】となります。ただ、私たちはこの字のように、
単に“大人が児(子)を育てる”ことが育児とは考えていません。
「子どもは、親を育てるために生まれてくる」
この言葉のように、親(大人)自身が、子育てを通して“自分が育つ”という姿勢こそが、
子どもが育つために何より大切な要素だと考え、【育自】と表現しています。
ほしのさとでは、保護者と学校スタッフが、子どもの育ちを真ん中に対話する、
おとなの会や、保護者も主体的に学校行事などに参画することを通して、
学校にかかわるすべての人が、より善く生きる場所づくりを目指していきます。





メッセージ


運営法人
学校法人あけぼの学園
理事長安家 周一
子どもには天から与えられた才能がある
あけぼの幼稚園は2024年度創立70周年を迎えました。母、安家周子、父、安家茂美の強い願いで豊中市南桜塚の地に誕生しました。爾来70年、一人一人の善さを尊重する保育の数々にチャレンジしてきました。当時幼稚園は1年保育が主流でしたが、創立当初から3年保育を実施していました。手間暇かかることにも果敢なチャレンジでした。地域の会館などに出向き、未就園児親子に対する保育も当時から行いました。また、乳幼児からの健康教育として、口腔衛生や薄着教育などにも早期から取り組んでいました。昭和50年ころには、幼稚園に保育所の併設や、定型発達児と発達に様々な困難を抱えた子どもも迎えていました。
平成となり、一人一人の育ちを大切にするという価値観の幼稚園教育要領が策定されました。あそびは子どもが決める価値観を中心に保育環境の改革を行い、登園したら、今日誰とどこで遊ぶは「子どもが決める」という価値を中心に、子どもの観察から導き出された、園庭や保育室内の環境を設定することを大切に、プロジェクト型の保育が進みます。
この様に実践を支えたのは、熱心な保護者と教職員です。自分の子どもだけではなく、社会が良くなることに力を出したいという願いが、困難を乗り越える力でした。その間、幾度となく聴いたのが「あけぼのに小学校があれば」という言葉でした。50年ほど前に入職した私は「いつかは小学校を」と思いを強く胸にしまい込んでいました。2023年秋、NPO法人コクレオ森元代表理事の辻さん(元きのくにこどもの村学園理事)、代表理事の藤田さんとの出会いがありました。その後、猪名川町の熱心な担当者との遭遇によってそのチャンスは訪れました。
子ども一人一人に「天から与えられている才能」を、保護者とともに丁寧に見極め、手塩にかけて素敵なところが遺憾なく伸びていくような小学校以降の教育の実践ができる可能性に、大きな喜びと期待を感じています。これからの民主的で開かれた小さな学校の設立に注目いただき、ご支援、お力添えいただければ嬉しく思います。

運営法人
学校法人あけぼの学園
園長安家 匠
僕が六瀬ほしのさと小学校を創る意味
僕らが【ほしのさと】という名前に想いを込めたように、一人ひとりの光を丁寧な眼差しで見る。そして、それを包み込める学校を創りたい。そこが出発点です。
本当の意味で幸せに生きるということの土台には「自分自身(自分の光)を知っている」ということが重要だと思っています。自分は何が好きで、どういう性格なのか、どうやって学ぶことが好きなのか。そんな自分探しの旅を、乳幼児期からの教育の連続性の中で「自己の発見」➡「自己の確認」➡「自己の承認」➡「自己の確立」というフェーズを行ったり来たりしながら進んでいくのだと思っています。そして、そのプロセスにおいて6年間の小学校教育は、重要という言葉では片づけられないほど重要です。そして、この視点こそが今回の学校設立プロジェクトの根本的理念です。
一般的に乳幼児教育は“一人ひとりの興味・関心に基づいたあそびや生活を通して育ちを引き出す”ということが大切にされますが、小学校以降の教育に目を向けると、乳幼児期に育まれた子ども達の興味・関心よりも、大人の準備した“幸せに生きる為の方程式”に沿って学ぶことにフォーカスが当たりがちです。この教育のギャップこそが現代教育の問題点だと思っています。それでは、教育をどちらの方向に軌道修正するのか。それは文部科学省が令和の日本型学校教育の中で打ち出す“個別最適な学び”という言葉を見れば一目瞭然でしょう。そういう意味では、あけぼのが長年やってきた、本当の意味で一人ひとりの良さが尊重される場所を創る。これが学校創りのコンセプトです。
次に想いを込めたいのは、“どのように子どもを捉えるか”という子ども観です。例えば、現代の教育の仕組みは、何かと子どもを「束」で捉えるようにできているように見えて仕方がありません。学習の進め方や評価の仕組みなど、個々というよりは「束」感が強い。果たしてその仕組みは、子どもを一人の人間として尊重することに繋がっているのか。そこで育つ子ども達は本当の意味で、自分という人間に自信を持てているのか。卒園児の姿や保護者との会話、その他にも、実際の現代型教育を知れば知るほど疑問が湧いてきます。さらに、僕自身の公立中学校での3年間の経験も、その疑問を大きくする要因かもしれません。この当たり前のように日本に充満する子どもの捉え方が変われば、学校教育を通して幸せになる子どもが増えるのではないだろうか。もしそうであれば、その先陣をきっていきたい。今はそんな想いを抱いています。
今回の学校づくりにおけるもう一つの視点は、変化が激しく、予測が困難と言われる未来を見据え、現代教育を問い直すということです。現代はインターネットやAIの普及により、誰にとっても情報を得やすい環境が整うなど、ある側面から見ると、とても便利な時代になりました。そんな時代の9年間の義務教育(学校)の役割について、真剣に問い直す必要があると思っています。まず大切な視点は、急激に情報化が進んだ社会において、学校が子どもに情報や知識を教授する役割を担う時代は、とっくに終わったということ。僕が教育の要素の中で一番重要だと思っているのが、学び手の納得感や必要感です。子ども自身が学びに納得していたり、必要と感じたりしていることが何より大切で、その後に主体性や学びに対する意欲が連なってくるといったところでしょう。そうなれば、子どもは“学んでいる”という感覚ではないのかもしれません。学校教育の本質は、人に言われたことを言われた通りにこなす受動的な営みではなく、自らの興味・関心に基づいた実際の体験を通して、その時期に学ぶことが目指される課題に向き合っていくというような、子ども達が学びの主体になる教育だと思います。一所懸命(いっしょけんめい)という言葉がおもしろい。手をパーにして紙を叩いても突き破ることは難しいですが、自分の好きな(興味のある)指を1本突き出して押し込めば簡単に紙は貫ける。その際、拳の中にしまわれた4本の指も一緒に紙を越えてその先へいく。学校教育ではそんな感覚が大切にされるべきだと思っています。
「令和の不登校児は暇知らず」という言葉を耳にした時、例えばYouTubeを開けば、興味のあるコンテンツが目白押しで、知りたい情報が簡単に手に入る時代において、学びの主役である子ども達にとって、学校に行く意義や意味みたいな価値観が、変化していると感じると同時に、全国に34万人を超えると言われる、不登校児の増加の事実も妙に腑に落ちる。もう、子どもが今の教育に納得していないんじゃないか。そんなことも感じます。
自分が受けてきた教育を全肯定する気は全くありませんが、教育的な変革が求められる現代において、僕自身があけぼの幼稚園ときのくに子どもの村学園で育ててもらったことへの感謝を、今回の学校創りで少しでも社会に還元できればと思っています。そしてそれが、子ども達や保護者が幸せに生きられる社会を創るきっかけになれば、そんな嬉しいことはありません。
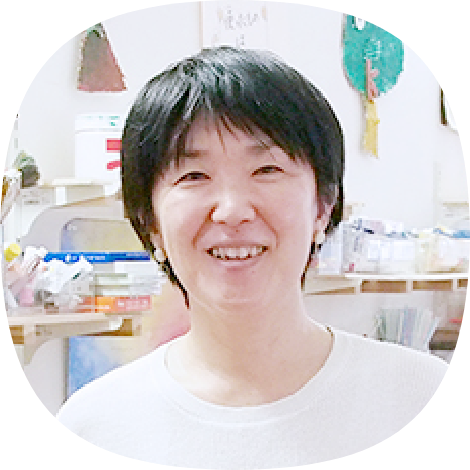
協力法人
認定NPO法人コクレオの森
代表理事藤田 美保
ほしのさと小学校設立への思い
私たちコクレオの森が、「2校目を創ろう!」と動き始めたのは、2017年頃。箕面こどもの森学園がほぼ定員となり、入学したくても入れないという人が増えてきていました。
2校目の設立を考えたとき、「無認可のオルタナティブスクールではなく、私立学校にしたい」というのが私たちの願いでした。それには、いくつかの理由があります。 無認可のオルタナティブスクールの場合、子どもたちの学籍は、地元の公立学校に置かなければならないという煩わしさがあります。また、子ども一人ひとりの興味・関心から始まる、対話や実体験を大切にする教育実践を行っていても、「無認可だからできるんですよね」と言われることがあり、何度も歯がゆい思いをしてきました。
2020年に学習指導要領が改訂され、学校でも、「主体的・対話的な深い学び」や「アクティブラーニング」が推奨されるようになりました。これらのことは、私たちが教育の中で大切にしてきたことでもあったので、「次に創る学校は、認可を受けた私立学校にしたい」という思いは、さらに強いものとなりました。
私立学校の設立を目指したとき、一つ大きな壁が立ちはだかりました。学校を設立したければ、学校法人になる必要があるのですが、既に私立学校が多い大阪や兵庫のような地域では、新規で学校法人になることが難しいということでした。
それなら、「一緒に学校を創れる学校法人を探そう」と考えたとき、最初に名前があがったのが学校法人あけぼの学園でした。あけぼの幼稚園やグループの保育園から、箕面こどもの森学園に何人かの子どもたちが来ていたことと、コクレオの森のスタッフがあけぼの学園の教育に共感していたことが理由でした。
実は、私の中に真っ先に浮かんだのも、学校法人あけぼの学園でした。オルタナティブスクールを始める前の2003年、偶然にも私は、あけぼの幼稚園のすぐ近くの南桜塚小学校で働いたことがありました。3年生の担任となり、社会でまちたんけんをすることになったとき、あけぼの幼稚園に下見に行ったことがあるのです。
初めて、あけぼの幼稚園の園庭を見た日のことを、今でもよく覚えています。一目園庭を見ただけで、ここは、子どもという存在を大切に考えているステキな幼稚園なんだと直感的にわかったのです。そのため、あけぼの学園の名前があがったときに、躊躇することなく賛成しました。
一方的に「あけぼの学園さんとなら学校を創れるんじゃないか」と思いはしたものの、どうしたら学校づくりへの思いを聞いてもらえるのか思案していたところ見つけたのが、あけぼの幼稚園で開催された映画「夢みる小学校」の上映会でした。
「この上映会に行けば、話を聞いてもらえるんじゃないか」という期待をいだき、あけぼの幼稚園の講堂に行きました。上映に先立ち、園長の匠さんと理事長の周一さんが、この上映会を開催する思いをお話される時間があったのですが、そのお二人のお話に、雷に打たれたぐらいの衝撃を受けました。
「これは、僕の母校の映画なんです」匠さんは、きのくに子どもの村学園の1期生で、周一さんは自由学園のご出身だというお話で、お二人とも、「いつか夢みる小学校のような学校を創れたらいいと思っている」というような内容でした。
きのくに子どもの村学園も自由学園も、心からリスペクトしている学校だったこともあり、「この人たちとなら、本当に一緒に学校を創れるかもしれない」と震える思いがしました。上映会が終わり、居ても立ってもいられない気持ちで、理事長のお部屋に行き、初対面の周一さんに自己紹介と経緯の説明をした後、「と言うことで、一緒に学校を創っていただけないでしょうか?」とお願いしたのは、映画終了から15分後ぐらいだったかと思います。
そこから、何度も対話を積み重ね、この「ほしのさと小学校」をともに立ち上げることとなりました。私たちだけではたどりつけなかった一条校(私立学校)を創るという夢を、学校法人あけぼの学園、猪名川町の方々と、ともに織りなしています。
コクレオの森のコクレオとは、「ともにつくる」という意味の造語です。こうして、偶然とも必然とも奇跡とも言える過程を経て立ち上がった「ほしのさと小学校」。入学してくれる子どもたちや保護者のみなさん、六瀬地域のみなさんとも一緒になって、ともにつくり続けていく学校でありたいと思います。
ぜひ、この学校づくりに、いろんなカタチでかかわっていただければ幸いです。
ほしのさと応援団


NPO法人コクレオの森 前代表理事
辻 正矩
六瀬ほしのさと小学校の開校に寄せて
私たちが長年待ち望んでいた2校目が、猪名川町六瀬に開校されることになり、感慨深いものがあります。2004年に箕面市内の民家で「わくわく子ども学校」(現:箕面こどもの森学園)を開校してから、2校目ができるまでに22年の歳月が流れました。
1校目を立ち上げる際、設立趣意書には次のような学校のイメージを描いていました。「立地場所は池または川のほとり。駅から5km以内。自然環境に恵まれた里山で、雑木林があり、日当たりの良い緩やかな斜面。敷地面積は16,500㎡(5,000坪)、校舎用地5,000㎡、運動場3,000㎡」 六瀬は、私たちのイメージに近い場所ですが、敷地面積が24,714㎡もあり、それを上回る理想的な環境だと言えるでしょう。
「学校は生徒数80人ほどの規模で、そこでは生徒とスタッフが生活を共にしながら、エコロジカルで民主的な教育が行われます。教師の役割は、将来必要となる知識や技術を一方的に教え込むことではなく、子どもたち一人ひとりの自立的な成長のプロセスを支援することにあります。この学校には、子どもたちが心ゆくまで遊び、学ぶための十分な時間と空間が用意されています。そのような教育環境のもとでこそ、子どもたちは抑圧から解放され、本来の好奇心を呼び覚まし、学ぶことの喜びを知り、自分らしい生き方を追求することができるでしょう。」 このビジョンが、六瀬の地で実現されることを心から願っています。

豊中市立南桜塚小学校 前校長
橋本 直樹
ほしのさとに教育の再生を期待して
長年、公立学校に勤める私が目指してきたのは「誰もが安心して学び、成長できる学校」という、いたってシンプルなものでした。しかし、この当たりから遠ざかっていく教育の現実を前に、息の詰まりそうになる学校に子どもたちを押し込めてはならないという思いで、日々の教育を進めていました。テストの平均点で都道府県や学校の値打ちを測り、点数で人を評価する中で、個々の子どもの姿や集団の中での子どもの関係性が見えなくなっているのが今の教育です。テストの点数を上げるために、新たなテスト導入するなどは、もはや教育と呼べるものではありません。
わたしたちは、「今公立がおもしろい」と打ち出し、教育制度の枠の中でうまく運用し、柔軟な対応を行ってきました。子どもたちが安心して学校生活を送るために、特別扱いをしてきました。それは一人ひとり違う、その子どもにとって必要な特別扱いです。日々、小学校チームとして奮闘してきましたが、制度の枠の中での運用にとどまらず、制度を越えた取り組み、さらには自分たちが制度をつくるのだという気概を持って学校運営にあたることなくして、教育の再生はありえないと考えるようになっていきました。それは、公立学校の限界を感じる日々でもありました。
そんなある朝、朝刊を前に釘付けになった記事がありました。「猪名川町の中学校跡地に小学校誘致」の記事でした。先を越されたという思いで記事を読み進めると、学校づくりの主体が、なんと私が勤める南桜塚小学校区にある、これまで注目してきた「あけぼの学園」であり「箕面こどもの森学園」ではないですか。繰り返し記事を読みながら、猪名川の地に出来るであろう小学校への期待は膨らんでいきました。「六瀬ほしのさと小学校」、なんと素敵な名前でしょう。自然豊かな地に、自由な発想のもと人間として開放された、民主的な教育が展開されることが教育再生の一歩となるのではないでしょうか。地域に開かれ、学校からも地域がよく見え、学校を中心として地域で、そして社会で子どもが育つ小学校として成長することを期待しています。

『夢みる小学校』監督
オオタヴィン
子どもは星だ
子どもたちは
ありのままの自分でいる権利がある
子どもたちは
毎日笑う権利がある
子どもたちは
1日中好きなことに熱中する権利がある
子どもたちは
1日中ぼーっとしていられる権利がある
だから 子どもは大人を超えていくのだ!
子どものなかには 巨大な星が眠っている
その可能性を削らず そのまま輝かせる場が “学校“であってほしい
国際情勢も気候もAIも大変動している今
大人たちのミニチュアを再生産している時間はないんです
もう一度言います 子どもたちは星だ
大人より巨大なんです
だから 大人たちのような哀れな流れ星(笑)にしちゃいけないんです
コクレオの森とあけぼの学園がつくろうとしている「ほしのさと小学校」は
なんと ちゃんと認可を受けた私立学校だという
ここで たくさんの子どもたちが輝くだろう
また 夢みる小学校がひとつ生まれる
僕は なんだか ありがたくってうれしくってしょうがないのです ♪
入学検討の方はこちら
入学を希望・検討の方は、
ぜひこちらのフォームからお申込みください。
寄付のお願い
個人・法人問わず、
学校づくりへのご支援を募集しています。

